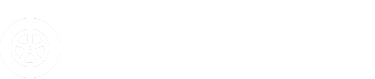「215/70R16のタイヤをインチアップしたいけれど、本当に自分の車に合うのか不安…。」
「乗り心地や費用の面でどんな変化があるのか気になる…。」
そんなお悩みをお持ちの方に向けて、本記事では215/70R16のインチアップに関する基本的な情報から、サイズ選びのポイントやおすすめタイヤまで、実体験を交えながら解説していきます。
- インチアップで見た目や走行性能はどう変わる?
- 車検に通るサイズ選びのコツは?
- 具体的な費用やおすすめの銘柄は?
上記の疑問をしっかり解消していただける内容となっていますので、ぜひ最後までチェックして、愛車にぴったりのインチアップを実現してください。
215/70R16とは? まずは基本を押さえよう

数字やアルファベットの意味

タイヤサイズの表記「215/70R16」を例に、項目ごとの意味をおさらいしましょう。
- 215:タイヤの断面幅(mm)
- 70:扁平率(タイヤの高さと幅の比率 / 70%ということ)
- R:ラジアル構造
- 16:ホイール径(インチ)
215mm幅で、扁平率70%のラジアルタイヤを16インチホイールに装着するサイズを示しています。

どんな車種に使われるのか

215/70R16は、SUVやクロスオーバー系の車、あるいは少し古めのミニバンや軽めの四駆などで見られることが多いサイズです。
たとえば下記のような車が代表例です。
- トヨタ 初代ハリアー
- トヨタ クルーガーV
- 三菱 エクリプス クロス(ベースグレード)
- 三菱 デリカD:5
- 三菱 アウトランダー
これらの車種では、オンロード用からオフロード寄りのタイヤまで多彩な選択肢が用意され、性能・スタイル・価格帯の幅が広いのが魅力です。
インチアップのメリットと注意点

ホイールを大径化する“インチアップ”は、愛車のイメージをガラッと変えるカスタマイズです。
しかし、メリットだけでなく、気を付けておきたいデメリットもあります。
インチアップのメリット

インチアップは、以下のようなメリットが挙げられます。
- 見た目がカッコよくなる
ホイールが大きくなるほど、足元に迫力が出てスタイリッシュな印象になります。SUVやクロスオーバーなら、より力強いイメージに仕上がるでしょう。 - ハンドリング性能の向上
扁平率が低くなると、タイヤサイドウォールのたわみが減少し、コーナリング時の安定感やステアリングレスポンスが向上する場合があります。 - ブレーキ性能の向上
タイヤ剛性が高まり、制動時の挙動が安定しやすくなります。高速走行が多い方や山道などをよく走る方は、恩恵を感じやすいでしょう。

インチアップの注意点・デメリット

インチアップには多くのメリットがある一方で、デメリットや注意点もあります。
- 乗り心地が硬くなる
扁平率が低いほど、タイヤのクッション性が下がり、路面の凸凹がダイレクトに伝わりやすくなります。快適性重視の方は要注意です。 - 費用がかさみやすい
大径ホイールや低扁平タイヤは価格が高め。4本セットだと予算オーバーになる可能性もあるので、事前にしっかりと相場をリサーチしましょう。 - 外径や幅の変化による車検リスク
タイヤの外径が純正比±3%を超えてしまうと、スピードメーター誤差が大きくなり車検に通らない場合があります。また、タイヤの幅が増えすぎると車体からはみ出してしまい、これもNGです。

215/70R16のインチアップサイズ例

インチアップは外径を合わせるのが鉄則

インチアップする際は、「タイヤ外径(直径)」をなるべく純正サイズに近づけることが重要です。
極端に外径が変わると速度計に誤差が出るうえ、車検に通らないリスクも高まります。
215/70R16のタイヤ外径(目安)
215/70R16のタイヤ外径は、計算によって求めることができますが、タイヤによって若干異なります。
【215/70R16のタイヤ外径の計算例】
215mm(タイヤの断面幅)×0.7(偏平率)×2+16(リム径)×25.4(インチ)=707mm
※タイヤメーカーや銘柄によって数ミリほどの違いが出る場合があります。
17インチへのインチアップ例

参考サイズ:225/60R17
インチアップする時はタイヤ外径を合わせます。
タイヤ外径の目安
- 215/60R17:690mm
- 225/60R17:701mm
- 215/70R16:707mm(16インチ)
タイヤ銘柄によって数mm程度の差あります。
なぜ「225/60R17」が候補になるのか?
- 扁平率が「70% → 60%」に変わる
- 元々の 215/70R16(扁平率70%)に対して、17インチにサイズアップするときは、「60%」という比較的近い扁平率が採用されることが多いです。
- 60にすることで、タイヤ外径をなるべく純正(215/70R16)の範囲内に収めやすくなります。
- 元々の 215/70R16(扁平率70%)に対して、17インチにサイズアップするときは、「60%」という比較的近い扁平率が採用されることが多いです。
- 外径はやや小さくなるが、±3%以内に収まる
- 純正の外径が707mm前後に対し、225/60R17では701mm。
誤差は2~3%程度となり、車検の目安である「±3%」に入る場合がほとんどです。 - 車検適合性の面でも安心度が高く、人気のインチアップサイズとなっています。
- 純正の外径が707mm前後に対し、225/60R17では701mm。
17インチへアップした際の特徴
- 見た目と乗り心地のバランス
- 扁平率が下がることで、ホイールが大きくなり見た目が引き締まる一方、16インチに比べるとタイヤのサイドウォールが薄くなるため、乗り心地に若干の硬さを感じることがあります。
- あまり極端に扁平率を下げていない分、街乗りや高速道路での快適性もそこそこ確保しやすく、見た目と乗り心地のバランスが良いのが利点です。
- 扁平率が下がることで、ホイールが大きくなり見た目が引き締まる一方、16インチに比べるとタイヤのサイドウォールが薄くなるため、乗り心地に若干の硬さを感じることがあります。
- ハンドリングの向上
- サイドウォールが低くなることで、コーナリング時のたわみが減少し、ステアリングレスポンスが向上することがあります。
- ワインディングなどでスポーティな走りを楽しむ方は、16インチ時よりもやや軽快なフィーリングを得られるでしょう。
- サイドウォールが低くなることで、コーナリング時のたわみが減少し、ステアリングレスポンスが向上することがあります。
- 価格帯や選択肢の多さ
- 17インチはSUVやミニバン、セダンなど、多くの車種が採用するため、タイヤ・ホイールともにサイズ展開が豊富。比較的手に入れやすいインチ数でもあります。
- 費用の面でも、18インチ以上に比べると少し抑えられる傾向があります。
- 17インチはSUVやミニバン、セダンなど、多くの車種が採用するため、タイヤ・ホイールともにサイズ展開が豊富。比較的手に入れやすいインチ数でもあります。

18インチへのインチアップ例

参考サイズ:235/50R18
タイヤ外径の目安
- 225/50R18:682 mm
- 235/50R18:692mm
- 215/70R16:707mm(16インチ)
銘柄によって数mm程度の差あります。
なぜ「235/50R18」が候補になるのか?
- 扁平率が「70% → 50%」に大きく下がる
- ホイール径を16インチから2インチアップの18インチへ変更するため、タイヤの高さをさらに低く設定し、外径が極端に増減しないようにします。
- 235という幅は、215よりも広いサイズ設定で、車種によっては迫力を求める方に選ばれるパターンとなります。
- ホイール径を16インチから2インチアップの18インチへ変更するため、タイヤの高さをさらに低く設定し、外径が極端に増減しないようにします。
- 外径は 692 mm と小さめ
- 純正が約 707mmに対し、235/50R18では約 692mm と誤差が約 15mm程度あります。
- 速度計の誤差が大きくなる可能性がやや高まりますので注意が必要です。
- 純正が約 707mmに対し、235/50R18では約 692mm と誤差が約 15mm程度あります。
18インチへアップした際の特徴
- 見た目の迫力がアップ
- ホイールが大きくなるほど、SUVでも独特の迫力やスポーティさが一段と際立ちます。ルックスを重視する方には大きな魅力となるでしょう。
- ホイールが大きくなるほど、SUVでも独特の迫力やスポーティさが一段と際立ちます。ルックスを重視する方には大きな魅力となるでしょう。
- 乗り心地への影響が大きい
- 扁平率が「70% → 50%」まで下がると、タイヤのクッション性が大きく損なわれます。
- 段差や路面の凹凸をよりダイレクトに感じるようになるため、街乗りが多い方や柔らかい乗り心地が好きな方には負担になる可能性があります。
- 扁平率が「70% → 50%」まで下がると、タイヤのクッション性が大きく損なわれます。
- ホイール&タイヤ価格が上昇しやすい
- 18インチ以上は高価になりやすく、タイヤ4本セット・ホイール4本セットで比較すると、予算が大きく上がるのが一般的です。
- タイヤ幅が広がる場合はホイールのリム幅も適合サイズに合わせる必要があり、選択肢が限られたり、コストがかさむケースがあります。
- 18インチ以上は高価になりやすく、タイヤ4本セット・ホイール4本セットで比較すると、予算が大きく上がるのが一般的です。
- オフロード走行が多い方は注意
- 50%という低めの扁平率は、オフロードや未舗装路での路面衝撃に対する耐久性が下がりがち。サイドウォールのダメージを受けやすくなる点に注意が必要です。
- 悪路走破性がメインという場合は、16インチや17インチをキープし、タイヤサイズにゆとりを持たせる選択が無難です。
- 50%という低めの扁平率は、オフロードや未舗装路での路面衝撃に対する耐久性が下がりがち。サイドウォールのダメージを受けやすくなる点に注意が必要です。
17インチよりさらに扁平率が下がり、乗り心地への影響やホイール価格の上昇が顕著になります。
見た目の迫力を重視したい場合に選択肢に入りますが、オフロード走行を多用する方は注意が必要です。

車種に合ったサイズ選びのポイント

- 純正サイズとメーカー推奨サイズの確認
取扱説明書や車検証で、純正タイヤサイズや推奨サイズをチェック。メーカーサイトで公開されている「適合表」も参考になります。 - 外径差±3%以内をキープ
法律上、速度計が正しい数値を示すことが求められており、外径差が大きいと車検に通らない可能性があります。 - ホイールのリム幅・オフセットを考慮
タイヤ幅が増える場合、ホイールのリム幅も広げる必要があります。ホイールオフセットが合わないとフェンダーやサスペンションと干渉する可能性大。適合確認がおすすめです。 - ロードインデックス(荷重指数)の確認
SUVやミニバンは積載量が多くなることがあるため、ロードインデックス(タイヤが支えることのできる荷重能力)を下げすぎると走行中の安全性に問題が生じます。
215/70R16のインチアップQ&A

Q1. インチアップにかかる費用はどのくらい?

- タイヤ代:1本2万~4万円程度(性能やブランドによって差が大きい)
- ホイール代:1本2万~5万円程度が目安
- 交換工賃:1台あたり1万~1.5万円程度(アライメント調整は別途1~2万円)
合計で15万~30万円ほどが一般的な相場です。
ホイールやタイヤのブランド・グレードにこだわるほど上乗せされるので、予算とのバランスを考慮しましょう。
Q2. おすすめの銘柄やブランドは?

- ブリヂストン「DUELER(デューラー)」シリーズ
オンロードでもオフロードでも、安定したグリップと剛性を発揮。SUV向けの定番ブランド。 - ヨコハマ「GEOLANDAR(ジオランダー)」シリーズ
悪路走破性を重視したモデルからオンロード快適性を強化したモデルまで、幅広いラインナップを誇ります。 - ミシュラン「PRIMACY SUV / LTX」シリーズ
長寿命と快適な乗り心地で定評あり。静粛性を重視する方におすすめです。 - ダンロップ「GRANDTREK(グラントレック)」シリーズ
街乗りと高速道路をメインに走る方に人気。ウエット性能も高く、安心感があります。
おもにSUV対応のタイヤが中心となりますが、使用シーン(オンロードメイン・オフロード・雪道など)をイメージしたうえで選ぶと失敗が少ないでしょう。
Q3. インチアップで車検に通らないことはあるの?

車検の注意点
- タイヤがボディからはみ出るとNG
- 外径差が純正比±3%を超えると速度計誤差が大きくなる
- ロードインデックス(荷重性能)が不足している場合も要注意
上記のポイントを押さえれば、基本的には車検対応が可能です。カスタムショップやディーラーで事前に相談すると安心です。

まとめ:215/70R16のインチアップで走りと見た目をアップグレード!

本記事では、215/70R16のインチアップについて以下のポイントを中心に解説してきました。
インチアップは、以下のようなサイズが挙げられます。
- 17インチ(215/60R17)
- 外径 690 mm 前後で、純正比±3%以内に収まりやすい。
- 見た目の良さと乗り心地のバランスが取りやすいため、街乗りメインのSUVオーナーに人気。
- 18インチ(225/50R18)
- 外径 682 mm 前後で、純正よりやや外径が小さくなる。
- スポーティな印象と迫力を得やすい反面、乗り心地や費用面へのインパクトが大きい。
- オフロード利用が多い場合は要注意。
インチアップは見た目を一気にカッコよく仕上げるだけでなく、ハンドリングや制動性能を高める一面があります。
しかし、一方で乗り心地の悪化や費用の増加、車検対応の問題など、注意すべき点も少なくありません。
- 「迫力を重視したい!」
- 「街乗りメインでも快適に走りたい!」
- 「オフロード走行が多いからタイヤの耐久性を高めたい!」
あなたの車の使い方や好みに合ったタイヤ・ホイールを選び、最適なインチアップを実現してください。
ぜひ本記事を参考に、理想のドレスアップを成功させてくださいね。